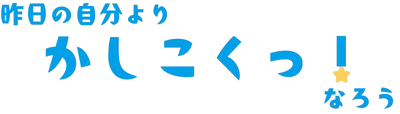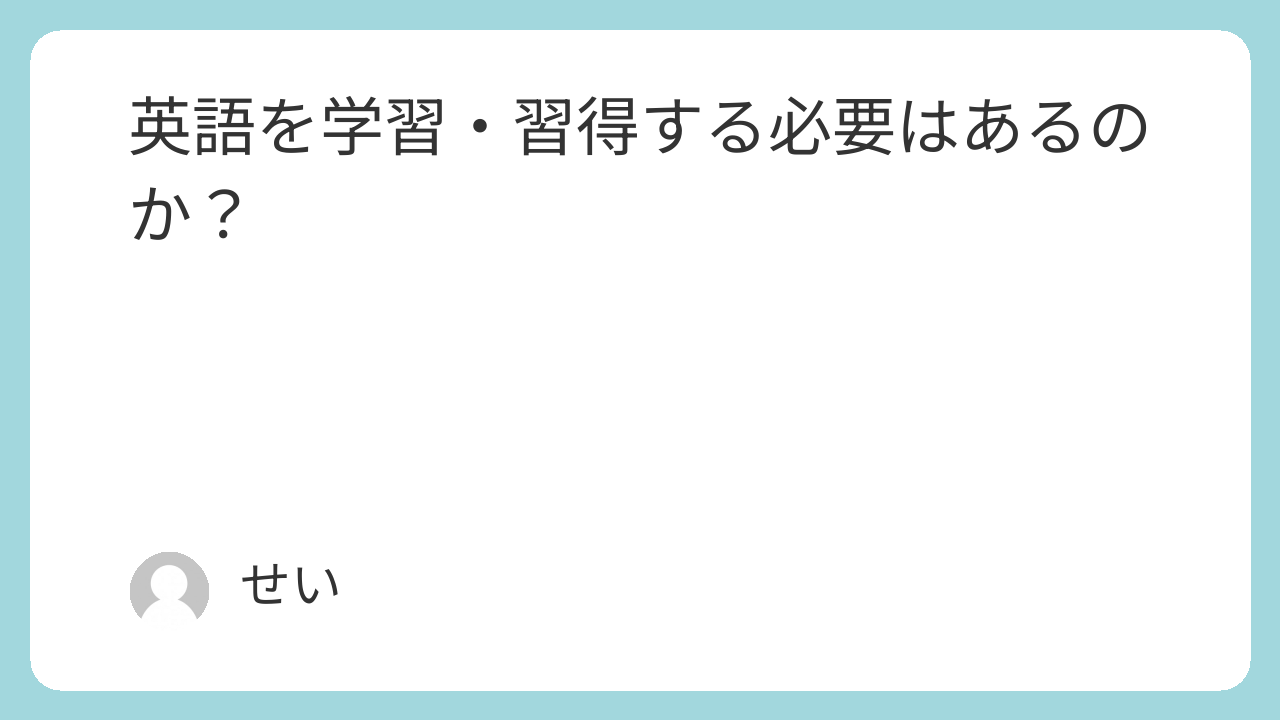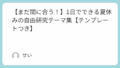英語(第2言語)を学習・習得する必要はあるのか?
「英語は学んでおいた方がいい」
「これからの時代、英語ができないと損をする」
そんな言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
グローバル化やインターネットの普及によって、世界中の人とつながれる時代になった今、英語は「国際共通語」としての地位を揺るぎないものにしています。確かに、英語が自在に使えれば便利ですし、情報へのアクセスも一気に広がります。
しかし私は、「英語を習得する必要は必ずしもない」と考えています。なぜなら、翻訳技術の進化があまりにも速く、人間が必死に第二言語を学ばなくても済む未来がほぼ確定しているからです。
翻訳技術の進歩で「言語の壁」は崩れつつある
ほんの10年前、機械翻訳といえばぎこちない日本語や、意味が通じるかどうか怪しい文章が多かったはずです。しかし今ではどうでしょう。Google翻訳やDeepLなど、AIを活用した翻訳サービスは、人間が読む上でほとんど違和感がないレベルにまで進化しています。
さらに、リアルタイムで音声を翻訳する機能も広まりつつあります。スマートフォンをポケットに入れておけば、外国人とその場で会話が成り立つ時代になりました。これから先5年、10年の進化を想像すると、翻訳のスピードも精度も今以上に向上し、日常生活やビジネスにおいて「英語を学ばなければならない」という状況はますます減っていくでしょう。
言語習得にはコストがかかる!
ここで忘れてはいけないのが、英語を習得するには膨大な時間と労力がかかるという事実です。
例えば、TOEICで満点(990点)を取るためには、一般的に2000〜4000時間以上の学習が必要だそうです。仕事で英語を使っている人や、英語圏に住んでいる人でない限り、この時間を確保するのは現実的にはかなり困難です。
また「日常会話ができる」レベルを目指す場合でも、ゼロから学び始めれば500〜1000時間程度は必要とされます。これは、1日1時間勉強しても1年半から3年かかる計算です。
つまり、英語習得は「投資」に近いものです。膨大な時間と努力をかけるだけのリターンがあるかどうかを考える必要があります。今のように翻訳技術が急速に進化している時代においては、「誰にでも習得が必要」という考え方は必ずしも合理的ではないのです。
AI翻訳の技術的背景
近年の翻訳技術の進歩は、ニューラル機械翻訳(NMT: Neural Machine Translation)という仕組みによって支えられています。
従来の翻訳システムは「単語単位の置き換え」や「フレーズごとの対応表」をベースにしていました。そのため、文脈を無視した直訳になりやすく、不自然な日本語が多かったのです。
しかしNMTは、文章全体をコンテキストとして捉え、文脈の流れを考慮して翻訳を行います。特に、Transformerと呼ばれる深層学習モデルの登場によって、翻訳精度は飛躍的に向上しました。Transformerは「注意機構(Attention)」を使って、文章内の単語同士の関係を柔軟に捉えることができます。その結果、主語と述語の関係や修飾のつながりなどを正確に処理できるようになったのです。
さらに、近年は大規模言語モデル(LLM)が翻訳にも応用されています。大量のテキストを学習したAIが、翻訳の文脈を理解し、より自然な表現を生成できるようになりました。これにより、「不自然な直訳」から「人間に近い翻訳」へとシフトしてきています。
今後の翻訳技術の展望
では、今後翻訳技術はどうなっていくのでしょうか。
- リアルタイム翻訳の普及
イヤホンやメガネ型デバイスと連携し、まるで自分の耳で聞いているかのように即時翻訳される未来が見えています。 - マルチモーダル翻訳
文字や音声だけでなく、映像やジェスチャーも含めて翻訳する技術。例えば、外国人が指さしながら話した内容をAIが解釈し、背景情報も含めて翻訳する、といった応用です。 - 個人適応型翻訳
ユーザーの話し方や語彙の傾向を学習して、その人に最適化された翻訳を行う仕組み。ビジネスならフォーマルに、友人同士ならカジュアルに、といった調整が自動で可能になります。
こういった技術の進歩を考えると、何百時間、何千時間と膨大な時間をかけて英語を学習する意味はないと思えてしまいますよね…。
それでも英語を勉強するべき人たち
ここで誤解してほしくないのは、「全員が英語を学ばなくていい」というわけではない、ということです。状況や立場によっては、英語の学習は避けられません。
① 学生(小中高校生)
最も現実的な理由は「テストで使うから」です。
どれだけ翻訳アプリが便利になっても、学校の定期テストや受験では使えません。つまり、将来英語を使うかどうかではなく、数年後、数カ月後、数週間後という“すぐ先の未来”に必要になるから勉強するのです。
② 英語を専門に扱う仕事を目指す人
英語教師や通訳、翻訳家、あるいは英語を使った国際的なビジネスの最前線に立ちたい人。こうした人たちは当然ながら、高度な英語運用能力が求められます。
機械翻訳が発達したとはいえ、文化的なニュアンスや細かな言い回し、人間同士の「心の通い合い」を完全に代替するのはまだ難しい領域です。そうした仕事を志すのであれば、腰を据えて学習する価値があります。
③ 一般人は「中学英語」くらいで十分?
一方で、多くの人にとっては高度な英語力は不要です。旅行で使う、外国人に道を案内する、ネットで少し調べものをする──その程度なら、翻訳機能と中学英語レベルの基礎知識があれば十分です。
英語を学ぶ「楽しさ」
ここまで「英語は必ずしも必要ではない」と書いてきましたが、私自身は英語を学ぶことが好きです。発音やアクセントのリズム感、アルファベットのシャープで洗練された文字の形、そして英語特有の表現の豊かさ。
洋楽、カッコいいですよね!
英字がプリントされたTシャツ、カッコいいですよね!
映画「ショーシャンクの空に」の終盤のREDのセリフ、カッコいいですよね!
I hope I can make it across the border.
I hope to see my friend and shake his hand.
I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams.
…
I hope.
実用性とは別に、「英語を学ぶことが楽しい」と感じる瞬間があるのです。
また、言語と文化は切っても切り離せません。アメリカ映画を字幕なしで観たい、イギリス文学を原文で味わいたい、韓国の音楽やフランスの映画のように、ある文化を深く楽しむために言語を学ぶ──そうした動機も立派な理由だと思います。
まとめ
結論を改めて整理すると、
- 英語は昔から「生きるために必須」ではなかったが、国際化とともに価値が高まってきた。
- しかし今は、翻訳技術の発展により、一般人が多大な時間と労力をかけて英語を習得する必要性はどんどん低下している。
- TOEIC満点には数千時間、日常会話でも500〜1000時間必要とされるなど、習得には大きなコストがかかる。
- ただし、小中高校生は「テストで必要」だから学習するべき。
- 英語を専門的に使う仕事を目指す人も必須。
- 一般人は中学英語レベルで十分。
- 実用性を超えて、英語を学ぶことを楽しむのも価値がある。
英語は「生きていくために必須のスキル」ではありません。必要な人はしっかり学べばいいし、そうでない人は翻訳技術に任せてしまえばいい。自分の立場や興味に合わせて、柔軟に考えればよいと考えます。
「必要だから学ぶ」だけでなく、「楽しいから学ぶ」という余裕のある姿勢で英語と向き合うのが、これからの時代に合ったスタイルではないでしょうか。